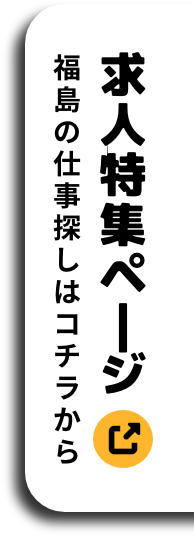COLUMN
連載

言葉にすること。会いにいくこと。やりすぎること。働き方研究家・西村佳哲さんに聞く、自分らしい人生を生きるためのヒント
これまでHOOKでは福島県相双地域の移住者へインタビューを行ってきました。その中で、生活に大きな転換をもたらす「移住」の困難さが語られることも少なくありませんでした。「移住は地域に強い思いを持った人がするもの」そう捉えている読者の方も少なくないと思います。それは移住者の声を届けるメディアであるHOOKにとっての大きな課題でもありました。
そうした課題に向き合いながらメディアを運営する中、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに私たちの日常生活には大きな変化が訪れました。リモートワークを導入する企業、オンラインで家族や友人とのコミュニケーションを行う時間は増加しました。そうした新たな生活様式が「当たり前」になる中で、今後の「住む」「働く」は大きく変化していくことが予想されます。この生活様式の大きな変化は「住む」「働く」を多様化させるものであり、より多くの人の「移住」という選択肢にリアリティを与えるきっかけになるのではないか。そうした考えのもと、HOOKではそれらの様々な働き方、暮らし方を実践されている方々について紹介する連載企画「コロナ以降の「住む」と「働く」を問い直す」をスタートさせることにしました。
今回ご登場いただいたのはプランニング・ディレクター、リビングワールド代表、働き方研究家として幅広く活躍する西村佳哲(にしむら・よしあき)さんです。西村さんは生まれ故郷の東京と徳島県の山間の神山町に拠点を持ち、双方を行き来しながらの二拠点生活を送っています。学生時代より地方に惹かれるものがあったという西村さんが神山を選んだ理由はどこにあるのでしょうか。また、若い読者に向けて、より良い暮らし方、働き方を見つけ出していくための指針をお話いただきました。

《プロフィール》
1964年東京生まれ。プランニング・ディレクター、リビングワールド代表、働き方研究家。武蔵野美術大学卒。大手建設会社を経て、現在は「つくる・書く・教える」など大きく3つの領域に取り組む。主に開発的な仕事の相談を受けることが多く、30代はものづくり、40代は場づくり、50代以降は建築計画やまちづくり、組織開発などの仕事が中心。2014年から東京と徳島県神山町での二拠点居住を始め、2016年より同町の「まちを将来世代につなぐプロジェクト」を進める一般社団法人 神山つなぐ公社に理事として参画。著書は『自分の仕事をつくる』(晶文社/ちくま文庫)他。京都工芸繊維大学や桑沢デザイン研究所、東京都美術館・とびらプロジェクト等で集中講義を担当している。
土に近い生活を求めて、東京と徳島の二拠点生活をスタート
徳島県の神山町へは、15年ほど前に仕事の依頼をいただいたことをきっかけに、年に1,2回訪れるようになりました。当時は東京を拠点にしながらも、どこか別の場所に生活の拠点を持てないかと模索している時期で、それこそ海外の街を歩いていても不動産の前で立ち止まってしまう、なんてこともしょっちゅうでしたね。東京生まれだったので、子どもの頃からどこか地方での生活には憧れがあり、未提出の宿題のように、ずっと心の端っこに残っていた気持ちがあったんです。
「もっと土や植物に触れながら暮らせるような場所で暮らしたい」という妻の希望もあって、ある時から本気で新しい土地を探し始めたんです。南伊豆や屋久島といった自然の美しい場所に訪れましたが、そこで暮らし、働く姿はイメージできず諦めました。かといって、地方都市には小さな東京のようなところもあって。そこで、神山町が選択肢に挙がってきたんです。住む場所として改めて見つめ直してみると、自然が豊かで町の規模もほどよく、これまで住んできた土地とは違う空気が流れていたことも気に入りました。そうした経緯で、東京との二拠点生活がスタートしました。
「何ができるか」ではなく「何をやるか」が問われる時代
いわゆる都市部と地方では、仕事の進め方やあり方が大きく異なります。都市部の仕事はアイデアを中心に人が集まっていきますが、地方での仕事はそこにいるメンバーを起点にアイデアを生み出していく作業。前者は思い描いたものを形にし、後者は想定外のゴールにたどり着くことが多いです。これはどちらが良い、悪いという話ではなく、性質の違いです。
なので、私が神山町でしている仕事では、いつもアイデアの手前に、具体的な「人」の存在があるんです。神山町は人口5000人少々、行政職員も100人ほど。行政との仕事といっても「お役所仕事」にありがちな壁を感じることは少なく、有機的な職場になっている。最近は住民を交えた話し合いの場で、若手の町職員が嬉しそうに話している姿が印象的ですね。
いまは「何をやるのか」が問われている時代だと思います。優れたビジネススキルを身につけたとして、そのスキルを持って何に取り組んでいくのか。搾取や刈り取りでなく、なにを育てていくのか。それを見直すタイミングじゃないのかと思います。また、コロナによる様々な変化を受け、仕事だけではなく、自分の生活を見つめ直す人も少なくないでしょう。
コロナの影響もあり、ここ最近はほとんどの時間を徳島の神山町で過ごしていますね。神山は山間にある町なのでコロナの影響で人が減ったりだとか、町の風景が変わるといったことはありませんでした。ただ、自分の仕事のなかでも好きなものである合宿形式のワークショップを開催出来なくなったことは大きいです。これも良い機会と捉えて、新たな仕事の方法を試行錯誤しているところです。
また、私生活では本を読むことの素晴らしさに改めて出会い直すことになりました。読書の時間は生活の中にやすらぎを与えてくれると同時に、新たな視点を与えてくれます。自分の中で忘れかけていた重要なものを取り戻したような心地ですね。
自分の生き方をみつけるためには、自分の言葉を探求し、人に会いにいくこと
自分の人生を生きたいと思ったら、今その瞬間にできることがあります。それは「自分の言葉で話す」ということです。自分の言葉で話すということを実践できている人はそう多くありません。どこかで聞いたり目にした言葉を使うのでなく、自分の言葉で話すことは地道な努力が要る。そして自分の言葉で表現するということは、自分を表現することの基礎になります。
そのためには、まず外から入ってくる情報を吟味すること、自分の中でその情報を処理する時間をしっかり持つことです。そして、自分が考えたことというより、感じたことを言葉にする機会をつくる。人に話す、書いてみるなどしながら、フィットする表現になっているかどうかを確かめること。気持ち悪いなと思ったら逐一直していく。そうすることで自分の言葉というものが出来上がってきます。
もう一つは、本やウェブの記事を読んで気になった人がいたら、触れる機会をつくることです。例えば、メディアなどの発言に感銘をうけ、その人に興味を持ったと想定します。しかし実際会ってみると、話と行動が一致していない、という場合も少なくありません。やはり、実際に会うというのは重要なんですね。若い人に関心をもたれることを嫌がる方はそう多くありません。自分のなりたい姿がわからないときは、自分の興味に当たっていくことが大事です。
私は若い頃に取材を通じてプロダクトデザイナーの柳宗理さんにお会いすることができました。もう亡くなられてしまいましたが、会った時の時間はいまだに忘れられません。世界というものを信頼している姿勢、といったらいいのでしょうか。彼の存在感とともにその感じが思い出されます。そして彼の活動からは「身近なものでまず作り始めてみる」ことがいかに大事かを学びました。
ある人は探求心、ある人は健やかさ、ある人はあっけらかんとした姿。私が出会い、影響を受けた人は多くいますが、いずれも少し一緒に過ごした時間のなかで、「こんな風に世界にいられるんだ」という感覚を、私が一方的に授かったように感じています。
やりたいことを「過剰なほどに」やることで次のステージが見えてくる
仕事をする上では、どんな環境であっても「やりすぎること」は大事なように思います。若い時分なら尚更です。
スキーやスノーボードのようなスポーツでは、体重を前にかけることでコントロールをすることができる。仕事でも同様に、体重を少し前にのせていることが大事なのではないかと思います。私が以前取材した大阪のガス会社勤務の方のお話です。彼は一企業に務めるサラリーマンですが「頼まれた仕事が10だとしたら、その仕事をしっかり形にした上でプラス5を仕事に加えるようにしている」と話していた。ある地域の仕事でパレードの企画を考えることになったそうなのですが、彼は通常の資料にプラスして「世界のパレード」という調査レポートを提出したそうなんです。パレードはどんな歴史があるのか、人類にとってどんな意味があるのかなどを調べていくうちに彼自身はパレードを通して社会の成り立ちに興味を持ち、別の仕事にも繋がっていった。合格点を目指すのではなく、要求されたこと以上のものをつくることで新たな出会いがあり、世界が広がっていくのだと思います。
以前学生から「卒業したら、嫌な仕事でも我慢して働かなきゃいけないんですよね?」と聞かれたことがあります。その子は周りの大人を見てそう感じたのでしょう。周りの人が我慢して働いているように見えているんですね。若い人は、私たちが思う以上に上の世代の姿をよく見ている。でも若い人に言いたいのは、「惹かれない人の姿を見続ける必要はないし、やりたいようにやればいい」ということです。いろいろな人がいる。楽しく働いている人がいる。光を感じる場所にいけばいいんです。
(2020/9/2取材)
-
取材:高橋直貴、宗形悠希
執筆:高橋直貴