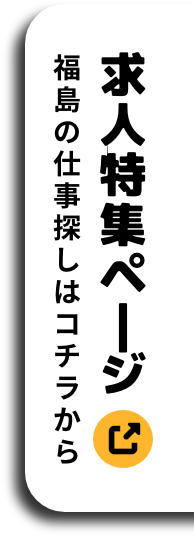INTERVIEW
インタビュー

飯館村から日本伝統の刃物を。世界へ羽ばたく鍛冶屋「二 瓶刃物」の挑戦(前編)
株式会社 二瓶刃物 刃物の館やすらぎ工房
代表取締役 二瓶 貴大 さん
福島県の浜通りに位置する飯館村は、「日本で最も美しい村」のひとつに選ばれ、豊かな自然に恵まれた小さな村です。
ここに工場&ギャラリーを構えるのが鍛冶屋「刃物の館 やすらぎ工房」。代表の二瓶貴大さんは、福島市で刃物販売やメンテナンスを生業にしていましたが、鍛治職人の減少と海外需要の高まりを受けて、職人の道を歩みはじめました。
工場を訪れると、もともと幼稚園のホールだった一室には金属を加熱する炉や大きな機械がいくつも並び、併設するギャラリーは洗練された空間が広がっていました。
二瓶さんが作る刃物は、プロの料理人や世界にも認められ、アメリカやカナダ、ヨーロッパ、アジアにまで輸出しています。日本の伝統を世界へ発信する二瓶さんですが、どのようにして現在の道に進まれたのでしょうか。
自分でビジネスをするため、家業へ

2019年、飯舘村の旧幼稚園の跡地に工場を構えた鍛冶屋「刃物の館やすらぎ工房」は、鍛造から仕上げ、柄すげまで一貫して生産し、約10種類の包丁を製造しています。
現在も福島市で刃物の販売・メンテナンス業を営む“刃物屋さん”の4代目となる二瓶さんが、「鍛冶の伝統を絶やさないように」と製造部門を立ち上げました。
「実は、家業を継ごうと意識したことは今までありませんでした。それまでは県外の企業に勤めていたのですが、30歳を目前としたときに、ふと『自分の実力って何だろう』って考えちゃったんです。企業の看板を背負って仕事をしているけど、その看板をはずしたときに何が残るんだろうって……」
自分の実力で勝負したいという想いが強くなった二瓶さんは、悩んだ末に実家の家業を継ぐという選択をしました。しかし、父・信男さんは、「給料も払えない」と賛同しなかったといいます。それでも二瓶さんは、押し通すかたちで覚悟を持って家業に入りました。
危機感から鍛冶職人の道へ
刃物販売やメンテナンス業に取り組むと、業界の課題が見えてきました。後継者が育たず、高齢化で鍛冶職人が減少していく一方で、品質の良さに注目する人が増え、海外からの人気は年々高まっていました。

「職人さんが減っているのに需要が伸びているので、地方の小さな刃物屋には商品が回ってこないんですよ。このまま販売だけを続けていたら店は潰れてしまうし、職人がいなくなったら鍛冶の伝統が途絶えてしまいます。それなら自分がやろうと思ったんです」
二瓶さんは自らが職人になる道を選びます。取引先であった新潟県三条市の鍛冶工房に「修行させてほしい」と頼み、家業を営みながら1ヶ月のうち1週間泊まり込みで修行をする生活を5年間続けました。
「鍛冶の技術は言葉で説明するのが難しくて、感覚的な領域が大きいと感じています。同じ道具、同じ機械を使ったとしても、師匠と同じものは作れません。何度も自分で試して感覚を磨き、探っていくような作業です。今も習得できたとは思っていませんし、それほど奥深い世界です」
二瓶さんは職人としての技術を身につける一方で、自社工場を持つための準備も進めていました。鍛冶で必要な機械設備の知識や設置方法も習得し、同時期に工場探しもスタートさせました。
飯館村との出会い
しかし、店舗のある福島市はもちろん近隣の市町村に足を運んでも、大きな音や振動が出る鍛冶屋の工場に合う物件はなかなか見つかりませんでした。3年かけて、40件以上見て回っても決定にはいたらなかったそうです。
震災から6年が経過した2017年、飯館村で避難指示が解除されるという新聞記事を目にしました。「飯館村なら条件に合う建物が見つかるかもしれない」と思った二瓶さんは、次の日すぐに村役場を訪れました。
役場の職員はこれまでにないほど親身になって対応してくれたそうです。いくつか候補地をあげ、何度も検討するなかで元幼稚園の園舎に決まりました。

「実は取り壊しになる予定の建物だったと後から聞きました。鍛造に使うスプリングハンマーという機械は、地下構造から色々設計する必要があり、音や振動もあるので場所を選ぶんです。役場の皆さんが親身になってくださったおかげで理想の場所に出会えました」
難航していた場所が決まり、ようやく独り立ちの時が来ました。村の避難指示が解除された2年後の2019年、刃物製造がスタートしました。
-
取材日:2024年12月
取材、執筆:奥村サヤ
写真、コーディネート:中村幸稚