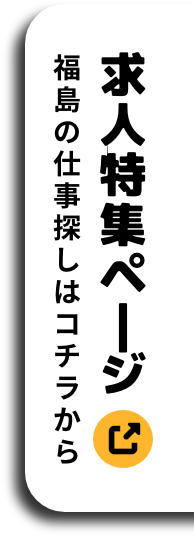INTERVIEW
インタビュー

ドラム缶パッキンのシェア率95%の「ミズホ 金属」が南相馬市で描く未来とは(前篇)
ミズホ金属株式会社
代表取締役 岡田真一さん
2024年4月に南相馬復興工業団地に工場を新設した「ミズホ金属株式会社」は、ドラム缶部品を製造し、社会貢献、社員満足、顧客満足の3つを軸に南相馬市で新たな産業の形を創造しようとしています。
「『ドラム缶部品と言えば南相馬、南相馬と言えばドラム缶部品』と世の中に認識してもらえるようになるぐらい、ここでがんばりたい」と話す代表取締役の岡田真一さんに、この町で描く未来を伺いました。
ドラム缶は日本経済の根底を支える産業だ

ミズホ金属は、1979年にドラム缶の部品を取り扱う会社として東京葛飾区に誕生しました。ドラム缶部品に特化した専門商社という独自のポジションを確立し、日本全国のドラム缶メーカーとの取引を拡大。市場シェアを確実に高め、現在はドラム缶用パッキンの国内シェア95%を誇ります。

「ドラム缶って普段目にすることはありませんよね。でも、ガソリンや灯油、塗料、化学薬品、医薬原料に至るまであらゆる液体や工業材料を入れて運搬・貯蔵していて社会のインフラに重要な役割を果たしているんです。ドラム缶がもしなくなったら、日本の経済自体を揺るがすことになると思います。我々はその一部であるパッキンを製造しているので、責任重大です。ドラム缶が日本経済の根底を支えていると言っても過言ではないんです
」
社会インフラを止めないため、製造業への挑戦
OEM製造品を販売してきたミズホ金属の転機は、2016年のこと。ドラム缶パッキン市場約30%のシェアを持つ主要な仕入れ先であるゴムパッキンメーカーから「廃業したい」と連絡を受けたのです。理由は、社長と息子である専務の親子間の対立でした。

「社長と専務のケンカがすごくてね、連絡をもらってケンカを止めに行くこともありました。急いで会社へ行くと、50メートル手前ぐらいから大ゲンカの声が聞こえてくるの(笑) 専務は『このまま続けたら自分がダメになりそうだ』と言うし、社長からは『うちの会社を買ってくれないか?」って相談されるし。それで、専務に『うちが会社を引き取るから、ミズホ金属の社員として製造を続けてくれないか?』と聞くと、『それならやる』と
いうんです」
とはいえ、買収するには大きなリスクがありました。ミズホ金属はそれまで商社であり、製造業は未経験。社内には製造ノウハウをもつ人材もいなければ、機械の操作方法や材料の知識もありません。
けれど岡田さんは、ドラム缶のパッキンは社会のインフラにとって重要な部品であること、そして供給を途絶えさせるわけにはいかないという使命感から製造業への参入を決断します。
経営不振から改革へ。工場拡大を計画

ゴムパッキンの製造を始めたミズホ金属でしたが、利益は出ず赤字続きでした。製造は手間ばかりがかかり、もう止めてしまいたいとさえ思ったそうです。
2018年、岡田さんは経営不振を払拭するために、藁にもすがる思いで稲盛和夫氏が主宰の経営者塾へ入ります。ここで、経営に対する考え方を根本から見直し「儲からない仕事を儲かるように」という新しい経営哲学を身につけ、経営改革への覚悟を持ったと言います。
2019年には工場を統合し、設備投資を実施。マンパワーで行っていた製造工程を自動化し、製品の品質向上とコスト削減を実現しました。この決断以降、大きく収益を伸ばしていくこととなります。さらに、新たな工場を展開するという計画まで持ち上がりました。
「実はバングラデシュ人の従業員のために、バングラデシュに工場を建てようという計画を立てていたんです。里帰りは会社の経費で行き来できるし、有休を使わなくてもいいでしょう。でもそのころ、コロナ禍になり構想が頓挫してしまったんです」
そんなとき、南相馬市の工業団地へ進出した知り合いの企業から「環境もいいし、岡田さんも来てみない?」と声をかけられたそうです。これが、ミズホ金属と南相馬市の出会いとなりました。
(後編へ続く)
-
取材日:2024年9月
取材、執筆:奥村サヤ
写真、コーディネート:中村幸稚
-
ミズホ金属株式会社
http://mizuho-k.co.jp/